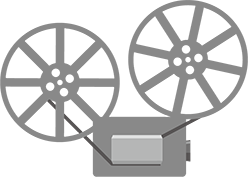2023年4月22日(土曜日)、横須賀市文化会館大ホールでおこなわれた、ドキュメンタリー映画『Yokosuka1953』の監督、木川 剛志さんより、メッセージエッセイをいただきました。
No.128 令和5年4月15日発行「16ミリ試写室だより」掲載
横須賀を旅して
映画監督・和歌山大学観光学部教授
木川 剛志
2018年9月末、初めて和歌山から横須賀に向かった日のこと。横浜駅から乗り込んだ京急快速特急は、外の雨のせいか窓ガラスはくもり、深まる夜の黒さを背景に、何か昔の映画の中に迷い込んだような、不思議な旅を予感させるものだった。横須賀中央駅。ホテルニューヨコスカにチェックインし、ロビーのバーで少し飲んだ後、ドブ板を歩き、大滝名店ビルの古い店で昔の話を聞いた。
部屋に戻り、持参した戦後間もない頃の混血児の方々について書かれた本を読んだ。
東京の川に混血児の嬰児が浮かんでいたこと、横須賀の街角に立っていた女性たちのこと。黒く鬱屈した空気を想像した夜だった。
映画YOKOSUKA1953はこんな私と横須賀との偶然の、しかし必然とも言える出会いから始まった。
研究調査のコツを聞かれることがある。私の場合は単純で、まずは現場で昼食2回と夕食3回を食べること。もちろん1日で。飲食店は人拠り所、そこでの会話で土地の空気を感じることができる。そして、目的があっても要件はこちらから切り出さないこと。会話が進むと向こうから「どこから来たんですか?」「和歌山からです」「え?和歌山から、なんでそんな遠くから?」となってから初めて「混血児のお母さん探しをしています」と答える。そうするとこちらの話をしっかりと聞いてくれる。少しずつ少しずつ、急がずに関係を築くこと。
洋子さんと母は複雑な家族の形。それは当時の横須賀では、決して珍しくはなかった。しかし、時代とともにそんな家族はいつのまにかいなくなる。どこでどうしてるのか、地元の人たちの心の中にそれは残っていた。その欠けたピースの一つが今回の映画が見せたものだったのだろう。
過去の横須賀に向かった初めての日。ひどく無機質で悲しい色だったその世界は、地域の人たちと一緒に歩むことで、いつしか暖かい色になっていた。私の中の横須賀の風景、いや心象の変化がこの映画だったのかもしれない。
関連リンク